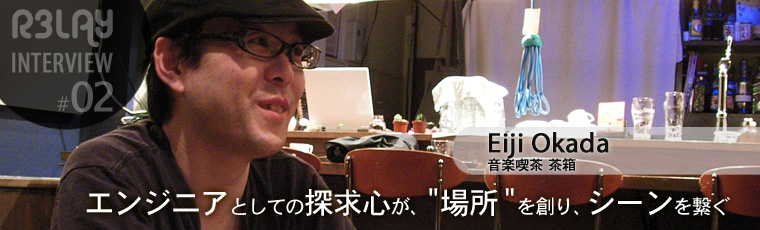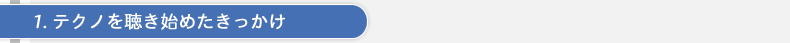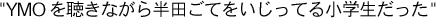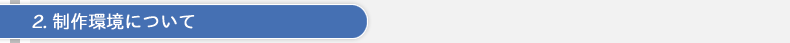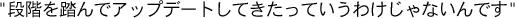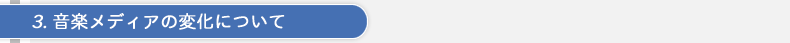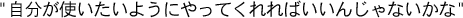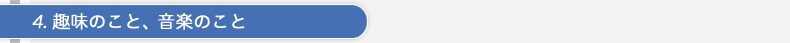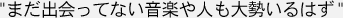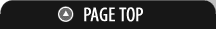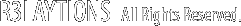R3LAYTIONS(リレーションズ) > インタビュー > 第2回:Eiji Okada (音楽喫茶 茶箱)
「サバコ」――日本が誇るテクノ外交官Tobyが、2007年にドイツのKartonからリリースした曲、そのタイトルは、東京・早稲田にある音楽喫茶「茶箱(さばこ)」にちなんだものでした。
カフェであるこのお店が、クラブやスタジオを意味する"箱(ハコ)"を名乗る理由は、店内に設置された巨大なスピーカーの存在にあります。国内有数の音響機器メーカー「レイオーディオ」のリファレンススピーカーで、このような飲食店に備え付けられるのは異例とのことです。
そして、そのサウンドのチューニングを行うと同時に、バーカウンター業務の全てをこなすのは、常連客から「エージさん」と呼んで慕われる店長の岡田英嗣さん。学生時代に電子工学を学び、卒業後はプロとして現場で腕を磨いてきた音響エンジニアです。
生粋のYMOフリークにしてシンセサイザー・マニアのエージさんに、ご自身の音楽的なルーツ、さらに技術者としての視点から現在のテクノシーンをどのように捉えているかという点について、お話を聞いてきました。
まだ「茶箱」に行ったことがない人はもちろん、「茶箱」を知り尽くした常連の皆さんも必読のロングインタビューです!
(2008年7月、早稲田「茶箱」にて)
- Eiji Okada 岡田英嗣
- 1973年生まれ。音響エンジニア兼カフェ経営者。ビンテージシンセサイザーを専門的に扱う楽器店、スタジオ機材卸の商社勤務などを経て、2003年1月に早稲田、諏訪通り沿いに「音楽喫茶 茶箱」をオープンする。当初より音の良さが評判となり、アンダーグラウンドのDJやクリエイターはもとより、プロのアーティストの間にも口コミで常連客の輪が広がっている。
近年はテクノ・ハウスなどのクラブミュージックだけではなく、ジャズを初めとする生音のライブも積極的に行うほか、ギャラリーを兼ねた昼のカフェ営業もスタート。自身も音楽サークル"THRUST"のメンバーとして楽曲制作を行うなど、多忙な毎日を送る。
1.テクノを聴き始めたきっかけ | 2.制作環境について | 3.音楽メディアの変化について | 4.趣味のこと、音楽のこと

さっそくですが、テクノを聴き始めたきっかけは何でしたか?
小学校の頃、うちの親父が、たまたまNHK-FMでやったYMOのライブの録音をテープで録ってて、それを何気なくかけてたのがきっかけなんですよ。確かイギリスのBBCが収録したハマースミス・オデオン公演※1っていう、すごい有名なライブなんですけど、だから、自分で意図的には聴いてなくて。親父からYMOについて詳しく聞いてなかったのと英語の歌詞だったので、しばらく海外のバンドだと思ってたんですよ。海外で、こういうテクノっていうか電子音楽でロックをやっている。だからロックだと思ったんですよね。
それから僕用にテープをダビングしてもらって、擦り切れるくらいまで聴いていたら、ある日突然それをテレビで見たんです。で、「あ、なんだ、これ日本のバンドなんだ」ってことを初めて知って。
じゃあ、お父さんがそういう音楽に興味があったんですか。
そうなんですよ。当時、昼の歌謡曲とか音楽番組をNHKでやってて、そのときにYMOがやってたらしくて、FMでライブ放送があるっていうんで、うちの親父が録ってたらしいんです。それをたまたま僕が聞いてて「これ、何?」って言って。小学校のたぶん2、3年生くらいの時。「これ、YMOだよ。『テクノ』ってのが流行ってるんだよ」って。
ということは、エージさんは最初に音楽を聴き始めたとき、既にYMOだったんですね。その前になにか興味があって聴いてた音楽はありましたか?
その前はねぇ、物心つくかつかないかの頃に、moogミュージックを聴いてたっぽいんですよね。例えば幼稚園のお遊戯とかでそういうのかかっていたような記憶がすこしあって。ちょっとピコピコした感じの音?そういうのに反応してたみたい。
いわゆる「刷り込み」ってやつですね。最初に買ったのはCDですか?レコードですか?
僕が最初に買ったのはCDでした。YMOのファーストアルバムですね。
家にはプレーヤーがなかったんです。親父はオーディオシステムを持ってたけど、貸してくれなかったから。ラジカセをもらって、ダビングしてもらってカセットテープで聴いた。その後お下がりのCDプレーヤーをもらって、これで何を聞こう、と。そのとき親父はクラシックを聴いてたから、親父のCDとかは聴いてたんです。だけど、一番最初に買ったのはたしかYMOかな。
その頃は、他の音楽は聴いていたんですか?
残念ながら、自分でレコードやCDを買うほどお小遣いがなくて、唯一やってたのは、近くの図書館で貸しレコードがあったんですよ。レコードとカセットデッキを繋ぐものはあったから、それを借りてきてテープに落として。だから自分で買うことは無かった。
むしろ子供のころ買ってたのは…、秋葉原で電子部品買ってましたよ(笑)。電子工作のために。小学校高学年くらいの頃なんですけど、そのとき『初歩のラジオ』っていう電子工作の本があって、それが発売されたら本屋さんに行って買ってきて、で、今日はこの工作をしようって決めたら秋葉原にパーツ買いに行って、作ってたの。サイレンを作ろうとか、交互に点滅するLEDのを作ろうっていうのとか。それはお小遣いで買ってましたね。
その時、「音楽」と「電子工作」はエージさんの中でリンクしてたんでしょうか?
してたんですよ。だからBGMもYMOなんです。YMOを聴きながら半田ごてをいじってる小学生って、気持ち悪いよね(笑)
もうその時点で自分の好きな音楽の世界があって、それをひたすら聴いてたと。そういう音楽を、身近な周りで聴いている人はいましたか?
YMOに関してはあまりいなかったと思います。音楽の情報交換をするようになったのは、中学になってからかなぁ。中学の頃ってちょうどバンドブームもあって、みんなでどのバンドがカッコイイかとか話してましたけど。
あと中学校のときは僕、吹奏楽部だったんで、その影響もあってかYMO以外はほとんどクラシックばっかり聴いてましたね。
そうなんですか。ちなみにパートは何だったんですか?
パーカッションでした。打楽器です。
ドン、チッ、ドン、チッ、ていう(笑)
パーカッションも高橋ユキヒロのドラムが好きだったのでそのパートに申し込んだという。当時も電子工作の本で「電子パーカッションの作り方」とかあって、回路を見つけては秋葉原にパーツを買出しに。で、いざ高校に進学するってことになったときに、電子工作とかに手馴れてたってこともあって高専に進学することに。これもたまたま近くに高専があったということなんだけど。育英高専という私立高専の電子工学科に進学しました。
初めてシンセを買ったのはいつですか?
高校生のときですね。入学祝いで、PC98と「ミュージ郎」※2を買ってもらったんですよ。楽譜は読めたから、YMOとか打ち込みをやって。それから高専の友達に教えてもらって、草の根BBSで音楽の友達が増えていった感じです。
でも、YMOを極端に好きっていう人があんまりいなくて。ゲーム音楽を耳コピしたりとか、特に「ミュージ郎」で言うと、CMからSoundCanvasになったと同時にアレンジものが増えていって、そういうのを聴き始めましたね。
エージさんが買ったときの「ミュージ郎」の音源って何でした?
CM-32だった。32と、32LとPってのがあって、Lってのが一番ベーシックなやつで、PになるとローランドのDシリーズとかPCMシリーズのROMが挿せるようになってて。そのあとCM-300とCM-500ってのが出て、500はROMも挿せるしその後のGS音源の元になったんだけど、すごい高くてね。やっと買えたのが「ミュージ郎Jr.」っていって一番ベーシックなやつ。中にデータも入ってるんだけど、再生できないのもあったりした(笑)
オリジナル曲の作曲もその頃から?
自作曲も作ったけど、コンピュータと音源があるからといって、自分でテクノを作ろうという気はなかったんですよね。
高校のときは、バイトやって、走り屋ってバイク乗り回すっていうのやってたんですよ。だから、楽器とか音楽にあまりお金をかけられなかった。だけど転機になったのは、たまたま楽器屋でSH-101がすごく安く売ってて、それを買って、高校2年だったかな。で、また楽器とか音楽に興味を示すようになって。
じゃあ、鍵盤があるシンセっていうのはSH-101が最初。
そうですね、それより前には家にヤマハのポータトーンもあったんですが、SH-101が自分のシンセサイザーとしては初めてですね。
その後、当時流行っていた草の根BBSなんかをうろうろしていたら、友達の紹介でX68000で曲作りをしてる人たちがいたんですよ。で、僕もX68000を買って、そういう人たちの曲を聴いてた。代表的なのが、カミシモレコーズのハリーさんっていう人がいて、今振り返るとすごくミニマルな曲を作っていて、そこらへんからまたテクノを意識するようになりました。それは高専も卒業してしばらくしてからだから95年か96年くらいですね。

その頃はクラブ方面の音楽の動向は知らなかった?
全く分かんなかったですね。それはね、高専卒業した後ですね。最も大きかったのはwatくん※3との出会いなんです。watくんとはなぜか東京BBSに共通の友達がいて、実は高校の同級生だったっていうの後で知って、彼もテクノを聴いてるっていう話を聞いて。テクノって僕の場合はYMOだったんですけど、彼の場合もっとゲーム寄りのほうだったらしいんですよね。
あと、当時ミニコミが流行ってて、レコード屋さんに行くとテクノのミニコミとかあったんですよ。それを見てたら僕らも何かやってみようよっていう話になって、それとほぼ同時期くらいにwatくんから「なんかテクノのレーベルが出来て、パーティーがあるらしいよ」って言われて行ったのが、フロッグマンの一番最初のイベント※4。そしたら、全然知らない曲ばっかりで、チャートとかリストとかもらえたんだけど、何が何だか全然分からなかった。これ何だろうなぁ、とか言って。
で、じゃあせっかくだから2人で何かやろうよっていう話になって、「LOOPS」っていうサークルを作った。その時に何か出さなくちゃねっていうことになって、watくんが既にDJとかに興味を持っていたから、ミックステープを作って配ったりして。
そのミックステープを作るきっかけになったのは、当時恵比寿にAnarchic Adjustment※5っていうファッションブランドのお店があって、そこにテープが置いてあったのね。その頃ちょうどゴアとかが流行ってて、DJやってた人たちがテープを売ってて。でもそれ人の曲の再販になっちゃうからさ、だからラブ・オファーって言って、500円以上入れてくださいとかっていう缶があったりして、それで買って聴いてましたね。
で、買うとフライヤーを付けてくれたりして、見るんですけどクラブ全く分かんないんですよね。でもwatくんとは一緒にクラブ行ったりして。それこそリキッドルームとかね。
なるほど。
実はそのあと面白い話があって、大学がつまらなくなっちゃって、ほんとは高専を出ればいい会社に就職できたんだけど、大学に入っちゃったんで、そこを中退したらほんとフーリーターっぽくなっちゃった。でも、その時にもう「LOOPS」とかやっていて、自分もちょっと音楽やりたいなと思ってたら、「サウンド&レコーディングマガジン」を読んでたらFive G※6っていう楽器店がアルバイトで技術者を募集してて、ダメもとで行ったら採用されちゃって。店頭で接客とかもやるようになって、そこから、いきなり広がりましたね。
実は、フロッグマンのアーティストさんがその楽器店に来ているということも分かった。Five Gって店は、ビンテージシンセサイザーの有名な店だから。
本当の、プロの現場のシンセや音響の知識はそこから。Prophet5なんか、当時でも50万とかしてたから買えなかったけど、でもそれを分解して直したりっていう、そういう知識を覚えさせてもらったのが大きいです。
あとは、その場で会ったアーティストがクラブイベントをやってて、「遊びに来なよ」とか言われて行ったりして。毎週末、仕事終わった後にクラブ行ってた。スタッフも若い連中だから、みんなで「今日リキッドでなんかあるらしいぜ」って行って、朝まで踊って、そのまま仕事場戻ったりとかして。若いからできることだけど(笑)
「茶箱」を作る直接のきっかけもそこにあるわけですね。
そうですね、お店に来るお客さんは当然のことながた音楽を作っている人ばかりなので、お客さんの要望を聞いていくうちに自分も知識が増えていった。そのころのお客さんってのは今でも仲良くさせてもらってるTOBYさんや、卓球さん、フミヤさんという今のテクノを牽引するすごい人ばかりで。当時はソニーがコンピだしたりしたテクノブームもあったから、海外のアーティストも結構遊びにきてた。ジェフミルズやハードフロアとかケミカルブラザースとか。今思えばすごい場所だったんですよね。
楽器メーカーの方とかとも知り合えるわけですよね。
そうですね。普通に新品も扱ってたから、営業で楽器メーカーさんとかスタジオさんとも知り合って、人脈が一気に増えましたよね。
95、96年くらいから4年半っていうと、ソニーテクノとかで日本にもテクノが根付き始めて、一番盛り上がっていたころですよね。
そうそう、だからお客さんであるアーティストさんから作品をもらったり、ライブに誘われていってみたらテクノのパーティーだったとか。それまでは意識的に当時流行ってるテクノにかかわるというよりかは、純然と店員とお客さんという立場でした。
そこから、「茶箱」に続くわけですか?
そのあとに、スタジオとかに機材を卸している商社に入ったんですよ。もともとその商社っていうのはFive Gと取引があって、引き抜かれて行ったんですけど、そこではもっと本格的なプロ用のスタジオ機材とかレーベル用の機材を仕入れてメンテナンスしたりっていう。音楽を作る現場用の機材を扱うようになったっていう感じです。
今となっては、「茶箱」はテクノとか、アーティストさんに慕われる店になってはいるものの、もともとは技術をやっていて、技術のフィードバックをした結果が「茶箱」であって、そこに音楽ありき、っていう感じじゃない。逆にそれは、僕としては正直寂しい部分ではあるんですよ。だけどこういう空間を作ることによって、それを使いたいっていう人が出てきたってことは、やっぱりそれは正解だったのかな。
あくまでも"プレーン"で、「僕がこれだからこういう店にします」ってことをしなかったことで、ジャズのイベントもやったり、ボーダーレスになったのはいいかなと思うんですよね。
そのほうがかえって良かったかもしれないですよね。
僕も曲を作るようになってきたんですけど、何で作ってるかっていうと、アーティストさんが曲を作るうえでどんなプロセスで曲を作ってるのか、どういったものを意図しているのかっていうのを勉強したくて。だから、僕はこういう曲を作ってリリースしたい、っていうのは正直あんまりなかった。裏方に徹したかったっていうね。
あくまで、技術的な視点から「知りたい」っていう、探求心の延長ですよね。
そうそう。その探求心から得た知識があったからこそ、Five Gとかで技術者としてやっていけたっていう面はあると思いますね。
- ※1 ハマースミス・オデオン公演1980年10月、ロンドンで行われたコンサート。翌1981年1月15日、NHK-FMが組んだYMO特集のなかで、BBCが放送したこの録音を含む音源がオンエアされた。
- ※2 「ミュージ郎」ローランドのDTMパッケージのブランド。音源モジュールとシーケンスソフトがセットになっており、PCを持っていればすぐに作曲が始められるとして、現在に至るまでDTMビギナーの定番となっている。付属する音源はクラス、世代により異なる。
- ※3 watくんDJ・トラックメーカーのwatさん。「R3LAYTIONS」の第1回ゲストDJのひとり。凄腕のゲーマーとしても有名。
- ※4 フロッグマンの一番最初のイベントインディーズレーベルFrogman Recordsの設立を記念して行われたもので、1993年12月31日、FFD渋谷で開催された。石野卓球、ケン・イシイ、田中フミヤ、YO-Cなど、黎明期の国内テクノシーンを代表するDJが集結したという伝説的なイベント。レーベルとしてのFrogman Recordsは、2008年1月をもって"Cold Sleep"という形で活動を休止している。
- ※5 Anarchic Adjustmentアナーキック・アジャストメント。サイケデリックなデザインで、90年代にクラブ系を中心に流行したサンフランシスコ発のブランド。
- ※6 Five G東京・原宿にある楽器店。ビンテージシンセサイザーの品揃えに定評があり、15年以上に渡って新品/中古の楽器・スタジオ機材を販売している。公式サイトはこちら。
続いて、曲作りの環境についてお聞きしたいと思います。今はPCベースですよね?
うん、PCベースで、Windowsマシンと、シーケンサーはFruity Loops。MIDIコントローラがmicroKONTROL一台で、ほとんどそれだけで今やってますね。家にはハードウェアシンセがあって、KurzweilのK2VXっていうシンセサイザーと、ヤマハのS80っていうピアノタッチのキーボード、あと僕のなかで切っても切り離せないYMOサウンドの要となっているTR-808。Prophet5は持ってたんですけど、有名な方に売りまして、その有名な方っていうのはスタパ齊藤さんなんですけど。
えー、そうなんですか!
僕、その時もうFive Gは辞めちゃってて、これはもうあまり使わないなってオークションに売りに出したら、買ってくれた人が実はスタパ齊藤さんで。いまだに持っているらしくて、何回か修理・メンテナンスしたりとかしたことありますよ。
そのProphet5※7、スタパブログで見たことあります(笑)
でもあれからコンタクトとってないから、僕がこういう店やってること知 らないと思うんですよねぇ(笑)
モニター環境はどんな感じでしょう?
家のモニターはねぇ、「茶箱」を作る前までは、ヤマハのNS10Mとか、いわゆるスタジオ専門のを使ってたんですよ。というのは、Five Gにいたときに、音に対する感覚をプロの人たちと一緒にしたかったので。
お店を作ってからは、ココでやってたりとかするし。今家で使ってるのはFostexのPM0.4っていう、一番ちっちゃいやつ。あれでもう十分ですね。
Fruity Loopsを使う前はCubaseを使ってたんですよ。で、さらにWindowsのCubaseを使う前は、AtariのCubaseを使ってたんですよね。これもまた面白い話なんですけど、97、8年くらいのときに、マッキントッシュの有名な専門店でアキバ館っていうのがあったんだけど、そこでなぜかAtariとCubaseのセットっていうのが売ってて、確かそれ2万円くらいだったんです。でも、マックの専門店だからみんな全然気づかないんですよね(笑)。ちょうどそこにDX7とM1のライブラリエディタがセットで売ってたんですよ。で買ってきて触ってみたら、あ、Cubaseってこんなに簡単に曲作れるんだ、って。
それまで、「ミュージ郎」触ってたころから多分4、5年くらい断絶があったんですね。その間は、自分の音楽を作るよりは、むしろX68000の音を聴いて楽しむっていう、リスナー側にいっちゃってて。でも、そこでまた曲作りに火が付いて。それからLOOPSでもちょこちょこ発表したりしてたんだけど、Five Gの仕事が忙しかったから、そんなに根詰めてやるっていうわけでもなかった。だから、お店を作ってからですよね。
いわゆるハードウェアシーケンサーを通ってないのは意外ですね。
Five Gにいたころはそれこそハードウェアオタクになってたから、曲は作らないけど、ローランドのSystem100-Mとか、MC-4、CV(電圧)で動くシンセサイザーをコントロールするためのシーケンサーとか持ってたけど、当時、90年代にテクノの人たちが使ってたMC-500とかカワイのQ-80とか、そういうのは一切買ったことないですね。
だから断絶があるの、どうしても。僕自身は、段階を踏んでアップデートしてきたっていうわけじゃないんですよ。ある日突然それがやってきた、っていうほうが多いんです。曲を作りたいからどんどんアップデートした、っていうわけじゃなくて、そこにある機材で遊んでたっていう感じですね。
それはやっぱり、Five Gっていう環境にいたからですよね。
そうですね。楽器屋さんはほんとに日進月歩で、どんどん進化した新しいシンセが出てきたっていう時代で、月ごとに新しいシステムになっていったいう感じなんで、目まぐるしかった。追っかけるのも大変でしたね。
- ※7 そのProphet5「スタパブログ」2006年6月30日の記事、「ビンテージ系音源モジュール」に写真入りで登場。
今、CDなりレコードなり、どれくらいのペースでどういったものを買ってらっしゃるんですか?
僕はね、ほとんどこのお店初めてからは、買ってないんですよね。というのも、インターネットが普及しているから、ネットラジオで聴いてる※8っていう感じですね。で、気になった音楽は、CDとかレコードとかアーカイブされているものじゃなくて、ライブを見に行きます。
へぇー。
だから、ここ最近はほとんど何も買ってないって言ってもいいくらいですね。ライブとかイベントに行って、そこで売ってたものを買ってくるくらい。
レコード屋にもあまり行かないんですか?
レコード屋にはたまに行く程度。というかお店に掛かりっきりで行く暇がほとんどなかったですね。当然クラブにも行く回数も減ったし。

でも、シスコの最終日とか、スパイスの最終日※9も現地でエージさんにお会いしましたよね。
それも、僕なりに思い入れのあるお店だったから。Five Gに居たときは仕事帰りに歩いていけたんですよ。で、欲しければ毎日買えたんですよね。今週は何が入ってるかなーって。仕事あがりの一杯ならぬ、仕事あがりの一枚。その店が無くなっちゃうっていうことで、行きました。
今は、積極的に動かなくても、「茶箱」っていうお店があって、お客さんが音楽を持ってくるじゃないですか。エージさんは、ご自身が聴きたい音楽に関してはそれで満足されている、と捉えていいんでしょうか。
今のところは満足してると思いますよ。ボーダーレスになってきて、これで十分かな、っていう。実際、お店で聞きたい音はあるんですけど、意図的に買いに行くかっていうほどでもないかもしれませんね。
これは率直な疑問なんですけど、エージさんが興味がある音は、ジャンル的にどこからどこまで、っていうのはありますか?
単純に言うと、歌謡曲はもうほとんど聴かないですよね。その代わり、テクノというジャンルだけではなく、インストゥルメンタルをすごくよく聴くようになりましたね。それは子供の頃、クラシックを聞いてたということに似ているところかもしれませんね。
現代音楽みたいなものはどうでしょう。
現代音楽はすごく興味があるんだけど、あまりに奥が深くてまだです。時間に余裕ができたら絶対聴きたいですね。時間は作るものだとは思いますけど、余裕があったらのめり込みたい部分はあるし、自分もそういう表現をしたいですね。
ところで、最近はあまりレコード店に行けないということで、かえって、レコードを買うという行為に関しては客観的な視点でご意見いただけるかと思うんですが、音楽のメディアが徐々にデータに移行しつつあることに関しては何かありますか?
これはもう、流通の変革なのかなと思います。前はレコードじゃないと手に入れられなかったものが、今はネットを介してデータとして販売したほうがお客さんの手に届きやすくなったから、そういうほうに移行してるんじゃないかなと思うんですよね。
データの"音質"についてはどうでしょうか。
元のデータによるんじゃないかと思ってますね。データでもいい音になる場合もあるし。デジタルデータは、人が感じられるアナログの音に変換するA/D、D/Aコンバータの特性でガラッと変わっちゃうんで、一概には言えないんですよね。
結局ね、いくらデジタルデジタルって言っても、完全にデジタルで持っていって、デジタルのまま音楽のデータとして蓄積されるっていうケースは、あんまりないんですよ。アーティストさんがアナログシンセサイザーとかデジタルシンセサイザーを使ってても、ミキサーとかアナログの電子回路のプロセスを通っていって、最後はA/DコンバータなりD/Dコンバータで44.1kHzのオーディオデータとして蓄積されるっていう、そこまでのプロセスは昔と変わらないんですよね。そこで完成したものが、デジタルデータでネットにストックされるとか、mp3っていう、より軽いデータにして、提供できるようにしているっていうことであって。
なるほど。マスターが出来た後の話ですもんね。
かといってアナログのレコードが古いのかっていうと、僕はそう思ってないし。音源を直接手で触れるっていう醍醐味もありますからね。
今お店で、PC持ち込みでPCでDJされる方っていうのは、エージさんの印象ではどれくらいの割合なんですか?
たぶん、3割くらいはもういますよ。今うちで若い子たちは、特にトランスとかって流通でデジタル化がすごく進んでいるみたいで、リリースもペースが早いから、もうデジタルでみんなやってるみたいですよね。
トランスは昔からCDJが多かったり、そういう変化は早いですよね。
恐らくは、アナログでプレスするまでの時間を考えたら、みんな早くリリースしたいっていうのがあると思いますよ。
確実にそういうスタイルのDJは増えてきている。
徐々に増えてきていますよね。この間有名なHiroshi Watanabeさん※10がうちでやってくれて、あの時もTraktorだったんですけど、やっぱり持ち歩くのが楽だっていうのが大きいみたいですね。でも家にあるのはレコードだっておっしゃってましたから、データでしかないものをデータで買っても、別にそれには違和感というか、躊躇するっていうのはないみたいですよね。
いわゆるPCDJシステムを使っているときに、細部の音質の違いは感じられますか?
厳密に言うとやっぱり感じます。デジタルは再生する機械に左右されちゃいます、元の音がね。同じ知ってる曲でデジタルとアナログで聴き比べた場合だと、細部の違いはありますよね。でも結局、アナログでも針とかで全然音が違うから、どれが気持ちいいかっていうと、それはその都度ミキサーとかのハードウェア機材のほうをチューニングしていかないといい音は追求できないかな、って感じです。
これはまだ良し悪しでは言えない、発展途中な気がするんですよ。だから、アナログじゃないとダメだとか、デジタルのほうが便利だよっていうのは僕の中ではあんまりないです。自分が使いたいようにやってくれればいいんじゃないかな。お店がそれに合わせるのは大変ですけどね。
- ※8 ネットラジオで聴いてる「茶箱」では、バー/クラブ営業時を問わず、常時無線LANアクセスポイントを開放している。
- ※9 シスコの最終日とか、スパイスの最終日世界に名だたるレコード店密集地である渋谷・宇田川町でも、特に有力だったCisco Recordsの一連の店舗と、中古テクノレコードの品揃えに定評のあったSpice Records 1号店が、それぞれ2007年12月10日と16日に、立て続けに閉店した件。閉店には一帯の用地買収が関係しているとされるものの、一般には、アナログレコード時代の終わりを象徴する出来事と評されている。
- ※10 Hiroshi WatanabeさんQUADRA、KAITOなどの名義でも知られるアーティスト。2008年6月6日「茶箱」でプレイし、ブログの中で「噂通りの素晴らしいサウンドで、誰もがみんなDJをここですればその気持ち良さを感じる事でしょう。」と感想を綴っている。

多趣味と伺っていますが、音楽以外の趣味にはどんなものありますか?
昔から続いてるのは釣りとバイクですね。でもバイクはお店の前で盗難にあってからご無沙汰してるかな。あとはアニメとか漫画も。
釣りのお話は最近あまり聞きませんが…。
うん、もうお店が忙しくてさ、だからなんとかして趣味の時間を作りたいなと思っていて。大問題ですよ。仕事人間でずーっと続けちゃってるから。
代わりがいないですもんね。
でも、今はスタッフを再雇用しまして、ようやく自分の時間というものを作ることができるようになりました。釣りにしてもバイクにしてもお金のかかる趣味ですよ。一度凝りだすと何十万も掛かっちゃう。そのうえで、シンセサイザーも趣味にしてるから(笑)
釣りはいつ頃からですか?バイクよりも前ですか?
小学校。地元が練馬だったんだけど、石神井公園とかで釣りしてた。フナとか釣れるんだけどさ、あの頃、電池駆動のラジカセを自転車のカゴに入れて釣り道具持っていって、YMOのカセットテープ聴きながら釣りしてる子供って気持ち悪くない?
あはは、そこも繋がってるんですか(笑)。電子工作しながらYMO、釣りしながらYMO。でも、そこまで持ち歩くってよっぽど好きなんですね。
そうそう、おかしな子供だったと思うんだよね。
その「自分の好きなもので自分の周りの空間を満たしたい」っていうのは、まさにココ(「茶箱」)のことですよね!
うん、だから今の「茶箱」ってその延長だと思うよ。それで商売やろうとしているから大変なんだと思うんだよね。だから「好きこそものの上手なれ」の連続で今に至っている感じですね。

でも、仕事兼趣味としての音楽の他に、たくさん趣味を持ってらっしゃることはいいことですよね。
そうですね、自分の好きなものが音楽以外にもあることが自慢になってると思います。今は音楽についてはそれこそ携わってる"仕事"ですから、趣味とは言えないところもあると思います。でも「茶箱」にいれば、自分の好きな音楽や、聞いたことのない音楽をお客さんが持ち込んでくれる。「茶箱」は固定の音楽ジャンルがない分流動性もあって、一見便利だけど、使い方を誤ると自分の生活が危うくなる(笑)。そうなると趣味とか言ってられない。ただ、ジャンルを固定しないで「茶箱」をもっと多くの人に知ってもらうことで、"いい音"の間口を広げたいというのは常に思っていることです。それによって自分が刺激をうけられるわけですから。まだ受身の段階で、自分の持ってる数々の趣味をやるにはまだしばらく時間が必要なのかも。
サイクルですよね。「茶箱」は今何年目でしたっけ?
5年を経過して6年目に突入しています。正直ここまで続けられると思ってませんでした。ですが僕が社会人始めてから、一番長い仕事になり、これからもこの仕事で行きたいと思っています。まだ出会ってない音楽や人も大勢いるはずなので。
こういう場所があるっていうのは、僕らにとってはすごくありがたいことなんです。先日もイエロー閉店※11という出来事がありましたが、そういう"場所"が減っているということについての危機感はありますか?
場所が減るという危機感はすごくありますね、「みんなどこで遊ぶの?」って。日本のテクノ総本山といわれた箱、マニアックラブが閉店※12したときに、TOBYさんからも「次は(次の世代)は君の番だからね」といわれた。マニアックラブ、新宿リキッドルーム、イエローが無くなったからといっても、それらの代理には「茶箱」はなれない。だけど、ほんの一握りの人でも「茶箱」を知ってくれて、同じ時期に体験した人たちが集える場になればいいなぁと思っています。
- ※11 イエロー閉店2008年6月21日、都内有数の大箱として16年の歴史を誇った西麻布のクラブSpace Lab YELLOWが惜しまれつつ閉店した。シーンを代表する老舗クラブの突然の閉店に、各所で驚きの声があがった。閉店はビル解体に伴うものとされているが、移転などについては未定。
- ※12 マニアックラブが閉店2005年12月3日、青山のクラブManiac Loveが閉店。オープン当初よりテクノに特化したクラブとして知られ、12年間に渡って国内外のDJに強い支持を受けていた。
終始気さくにインタビューに答えてくださったエージさん。「茶箱」が多くの人に愛され今もなお口コミで広がっている理由は、その音の魅力もさることながら、店長であるエージさんの人柄にもよるんだなと改めて感じました。
印象的だったのは、探求心に端を発した機械いじりが、クラブミュージックシーンとの出会いを経て、それを持続させるための"場所"を創り、守っていくという明確な目的を得て現在に繋がっている、ということ。エージさんが、音やそれを支える技術に対して常に真摯に向き合っているからこそ、そこを借りる私たちの気も引き締まり、いいパーティーを続けていけるんだと思います。
これからも、末永くお世話になります!
聞き手・写真:R3LAYTIONS(R-9,una)
- 音楽喫茶 茶箱
SABACO Music & Cafe - 早稲田、諏訪通りに面したビルの地下にあるカフェ/クラブ/貸しスタジオ。最高峰と評されるRey Audioのモニタースピーカーを擁するサウンドシステムと、現役音響エンジニアのオーナーによるチューニングにより、カフェを兼ねた空間としては異例の音の良さを誇る。
クラブイベントなどの夜間の貸切営業のほか、平日夜間はカフェ営業、日中はギャラリーを兼ねたカフェ「お昼の茶箱」などもある。また現在は、店長個人による音響機材の修理・カスタマイズも請け負う。詳しくは下記各サイトを参照のこと。
東西線「早稲田」駅より徒歩5分、副都心線「西早稲田」駅より徒歩12分。 - 〒162-0051 東京都新宿区西早稲田 2-1-19YKビルB1F
- TEL/FAX 03-5272-7385
- 営業時間:14:00-18:00(ギャラリーカフェ)/18:00-23:00(バー営業)
- 定休日:土日祝日(貸切利用日を除く)
- 第3回:Yousuke Kaga (Fountain Music) 「聴いたことのない音楽との出会いが、自分の世界を拡げてきた」
- 第2回:Eiji Okada (音楽喫茶 茶箱) 「エンジニアとしての探求心が、"場所"を創り、シーンを繋ぐ」
- 第1回:misutrax & TOMO-ARCHITECTURE (TOM-BOYS) 「2人の音楽少年・出会いからの10年と、その先の"LIFESTYLE"」