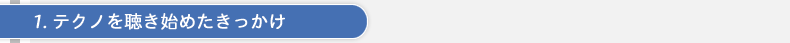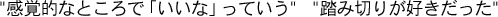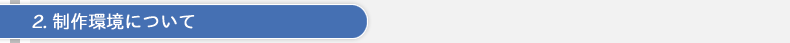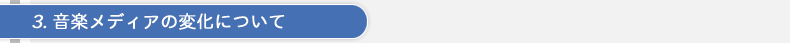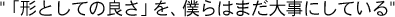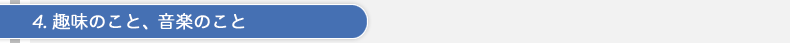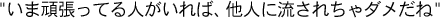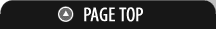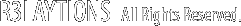R3LAYTIONS(リレーションズ) > インタビュー > 第1回:misutrax & TOMO-ARCHITECTURE (TOM-BOYS)
東京と山梨という別々の土地で、ともに少年期にエレクトロニック・ミュージックの洗礼を受け、1998年、大学の音楽サークルを通じて知り合った2人。現在はテクノポップ・ユニット「TOM-BOYS」として活動中の、「misutrax」こと深須(みす)さんと、「TOMO-ARCHITECTURE」こと杉山さんが、リレー・インタビュー第1回のゲストです。
出会いから10年を経て30歳となった彼らは、社会人として働く傍ら、今もなお作曲やライブなどの音楽活動を精力的に続けています。そのユニット名の由来は、母校である大学の学内ファーストフード店、「TOM-BOY」。YMOの『ライディーン』や『コズミックサーフィン』のカバー、そしていくつかのオリジナル曲を発表したあと彼らが次に取り組んだのは、共に多大な影響を受けたという、元クラフトワークのカール・バルトスによるElektric Music名義のトラック、"Lifestyle"のカバーでした。
変わらない音楽少年の遊び心を持つ2人に、今までの、そしてこれからの音楽にまつわる「ライフスタイル」について聞いてきました。
(2008年6月、高円寺にて)
- misutrax (写真左)
- 1978年生まれ。作編曲、プロデュース、シンセサイザー担当。12歳にして打ち込みに目覚め、数多くのシンセサイザーと共に青春を過ごす。98年、中央大学テクノ・ハウスサークル「ヴィニールハウス」在籍時に、TOMO-ARCHITECTURE、DJ Yonkawaとともにバンド「宇宙野菜」を結成。その後も「wavescan」、「MEESUTRAX」など数々のアーティストとの共同プロジェクトを経験し、プロデューサーとしても手腕を発揮する。80年代テクノポップ・サウンドとお笑いをこよなく愛する、根っからの音職人。
公式サイト:MISUTRAX'S WEBSITE - TOMO-ARCHITECTURE (写真右)
- 1978年生まれ。主に作詞、ヴォーカル担当。静かで知性的な詩の世界と、一見それに相反するような縦横無尽のパフォーマンスの才能を併せ持つ、「宇宙野菜」、「TOM-BOYS」のフロントマン。地元・山梨での音楽活動を経て、98年に大学でmisutraxと出会う。卒業後も「宇宙野菜」として度々ライブ活動を続けながら、07年8月、前身となる「V'z」名義での活動を契機にテクノポップ・ユニット「TOM-BOYS」を結成。翌08年2月には甲府で初の凱旋ライブを行い、好評を得た。
1.テクノを聴き始めたきっかけ | 2.制作環境について | 3.音楽メディアの変化について | 4.趣味のこと、音楽のこと

まずは、お2人のルーツをお聞きしたいと思います。もともと、テクノを知ったきっかけは何ですか?
TOMO-ARCHITECTURE(以下、T)僕は小学校高学年のときに、地元が山梨の南アルプス市なんだけど、運動会でYMOの『ライディーン』がかかって、それでなんか鳥肌がたって子供心に衝撃を受けたというか。そのときはまだそれがテクノポップとかいうことは知らずに、曲を聞いて「なんだこれは」って、戦慄を覚えたのがきっかけかな。
それを、音源として買ったのっていつ頃ですか?
T中学1年。クラスが一緒だった友人のLAMAZE※1の家に遊びに行ったとき、彼がベスト盤を持ってて、たまたま流したら「これ聞いたことある」ってなって、それで『ライディーン』っていう曲だってことを知って。91年だね。
僕は、今もそうだけど音楽を専門的にやっていたわけではないので、音が、なんか、感覚的なところで「いいな」っていう。そのあとLAMAZEからテクノポップのおすすめを色々薦めてもらって。
最初に買ったCDは何ですか?
T映画の『天と地と』※2のサウンドトラック。小室哲哉が音楽監督の。そのときはまだ小室哲哉とか知らなかったんだけど、映画を見たときに曲がなんか引っかかって。
じゃあもう、その時も知らず知らずのうちにシンセ的な音に惹かれたわけですね。『ライディーン』と同じく。
Tうん。まあ多分シンクラヴィア※3とか使ってたはずだから…
misutrax(以下、m)杉山くんの口からシンクラヴィアって聞いて、ちょっとなんかオレ、すげードキドキしちゃった(笑)
T(笑)たしかに僕は機材のこと疎いけど、あの…。
mいやいや、十分知ってるよ。普通の人シンクラヴィア知らないもん。
深須さんは最初に買ったCDって何ですか?
m最初に買ったCD?シューベルトの『魔王』※4。小4とか小5ぐらい。音楽の授業で聞いて、この曲は何だ、っていうんで。
それはすごいですよ!音楽の授業で、これだ、っていうのは。
m要はね、構成が、最初16分音符で「デデデデ…」っていう、やっぱそういうシーケンス的なやつが好きだったんだろうね。そのCDには10何曲入ってたけど『魔王』しか聴いてなかった。
そのときってもうピアノ習ってました?
mピアノはもう5歳とかから。姉が習ってたので、自分から習いたいって言って。
家にあったんですね。でも、そこから何で電子音楽に行ったんですか?
mあのね、踏み切りが好きだったの。踏み切りって、音もそうだし、システム的に完璧じゃない。電車興味ないんだよオレは。一切。踏み切りっていうこのシステム。音の光のパレードっていうかもう、ショーだよあれは。カーンカーンカーンっていう、自動的に降りてくるんだから、こう。音と光のファンタジー。

音と光のファンタジー(笑)。
m親がイトーヨーカドーとかに一時間くらい買いものに行ってるんだけど、オレずっと踏み切りにいる。ずーっと見てんの。小さいころの写真見ると、踏み切りで撮った写真ばっかり(笑)。日本各地の。
踏み切りがルーツですか。
mでやっぱ、小学生になるとファミコンですよ。ファミコンの音が気になるんで、テレビの前にラジカセ置いてよく音は録音してたね。ファミコンは小2で買ったから、『スーパーマリオ』出てすぐくらいかな。でも、『ドアドア』※5を買っちゃったんだけど(笑)。
子供のころってまだ音楽を音楽として認識してないですよね。アニメとかで曲がかかってても「なんとかの主題歌」っていうふうに聴いてて、別にそれって音楽として聴いてないんですよね。好きなアニメなりゲームに付随するものであって。
mでも、僕は付随じゃなくてそっちがメインだったかも。オープニングだけやたら見てるとかそういう、曲が聴きたいだけで。編集しだすのはもっと後で、小4とか5くらいになってからだね。同じ1小節くらいのフレーズをカセットテープに録音してループ作ってたね。
機材的なところはどうですか?
m小5でカシオトーン※6、小6でEOS(ヤマハEOS B500※7)。オールインワンなんで、弾くだけじゃなくて打ち込みも。
小6!相当早いですよね。
mカシオトーンでTM(TM NETWORK)弾いてたんだけど、物足りなくなって。なんでこのカシオトーンにはあの音がないんだろう、みたいな。
え、TMとかを意識的に聴き始めたのっていつ頃ですか。『魔王』の前ですか、後ですか?
m『魔王』と同じくらい。5コ上の姉の影響が大きくて、洋楽もロックも打ち込みとか幅広く聴いてたんで。数年後、TMにどっぷりハマったあと、姉に「聞かせなきゃよかった」って言われた(笑)。でも、他の流行りの音楽は全然。
好きな音楽の話題を学校でした覚えってありますか?音楽の趣味が合う友人とかいました?杉山さんは先ほど出たLAMAZEさんというクラスメイトがいましたが。
T彼は僕よりもっと広く深く聴いていて、流行ってるものは嫌いだったんだけど、僕はB'zなんかも好きだったし、友達とそういう話はしたよ。
m僕はね、中学のときはほんと話が合わなくて、同級生とT-BOLANがなんぼのもんじゃ、みたいなことでケンカをしたことがあるね(笑)。
(笑)
mTRFとかそういうの聴いてたんで。デビュー前から。ファーストアルバムが出るのを心待ちに待って買ったからオレ。だから全然話合わないから、アニメ部?マンガ研究部みたいなとこの子とaccessの話とかしてた。
それって高校でもそうでした?
mいや、高校になるとソニテク※8ブームが来るんで、ちょっと状況が一変しますよ。ヒップホップとテクノ、みたいな勢力がね。で、高校ぐらいになるとバンドとか音楽やる子が増え始めて、「隣町の高校にすごい曲を作る奴がいるぞ」みたいな情報が入ってきたりとか、イベントとかで会うとカセットテープを交換したりとか、してたよ。カセットもらったりとか。で、そいつんちに行って「おお、すげー」みたいな、「JUNOでこんだけ作ってんの」みたいなね。そのときは学園祭に向けてバンドもやってたから。テクノじゃなかったけど。KX-5でシンセベースを弾いて、曲によってはドラムも打ち込み。
杉山さんも高校時代バンドやってたんですよね。
TさっきのLAMAZEと2人で「インチキ桃」※9っていうバンドを。
m伝説の。
T僕もまだ山梨に居たんだけど、彼の家に行って、泊り込みで1曲2曲作るっていう。LAMAZEがギターで曲を作って、僕が詞を書いて、録音して、ジャケットも手書きで描いて。今も僕が帰省したときは同じようなことをしていて、それは中学高校のときから変わってないね。
- ※1 LAMAZE「ラマーズ」さん。「YOSUKE」という名義でも活躍中。TOMO-ARCHITECTUREさんの旧友で、現在も地元、南アルプス市で活動中のトラックメーカー/アーティスト。
- ※2 『天と地と』歴史小説が原作の大河ドラマ。1990年に角川により映画化され、テーマ曲を含めた音楽を小室哲哉が担当した。
- ※3 シンクラヴィアSynclavier。シンセサイザー、サンプラー、シーケンサーなどの音楽制作環境を統合した電子楽器。80年代当時は非常に高価で、小室哲哉が愛用していたことでも知られる。
- ※4 『魔王』19世紀、オーストリアの作曲家シューベルトが作曲した歌曲。日本では音楽の教材にも登場し非常に有名。
- ※5 『ドアドア』85年、エニックスのファミコン参入第1弾として発売されたゲームソフト。モンスターを誘導し、ドアに閉じ込めるアクションゲーム。
- ※6 カシオトーンカシオが発売している電子キーボード。初めて登場したのは80年で、楽器メーカー以外から発売されているキーボードとしては、価格と性能の点で現在も定評がある。
- ※7 EOS B500ヤマハのワークステーション。小室哲哉がイメージキャラクターを務め、TMNのコピーをこの一台で手軽に再現できる事から爆発的な大ヒットシンセとなった。
- ※8 ソニテクSONY TECHNOの略。90年代中後期、SME(Japan)が仕掛けた大々的なテクノ・キャンペーンを指す。海外アンダーグラウンドで活躍するアーティストを、初めて日本で紹介するなど大きい功績を残したものの、ジャンルの分散、シーンの縮小を受けて終了した。
- ※9 「インチキ桃」山梨・南アルプス市を拠点に現在も活動している、特定のジャンルにとらわれない雑食性音楽ユニット。主要メンバーはTOMO-ARCHITECTUREとLAMAZEで、作品ごとにメンバーが追加・流動している。
話は変わりますが、制作環境について聞きたいなと。今、作曲はPCベースですよね。その前のハードウェアシーケンサーの時代って長かったですか?
m長いですよー(笑)。最初はEOSなんだけど、一番時期長いのはSY77ってやつなんだよね。ヤマハのちょっとフラグシップなオールインワンシンセだったけど、当時。そこから、電気(電気グルーヴ)が使ってるっていうんでローランドのMC-50 mk2に行って。
SY77は16,000音しか入れられないんですよ。MC-50のほうがもうちょっと、倍くらい入ったんで。僕けっこう音数、細かく多いので、16,000音だと一曲終わらない場合があるんですよね。だから間引くの。今は容量とか気にしないんだけど、昔は同時発音数と、シーケンサーの容量を気にしながら、3和音の真ん中削ったりとか。色々やったよ。
PCベースに移ったのは、98年の「宇宙野菜」※10結成のとき。マックを入れて。
PCにしたのはどうしてですか?やっぱり、スペック的なことでしょうか。
mいや、電気が…。電気がパソコンに移ったし。
(笑)

m電気は昔W-30っていうローランドのサンプラーから、『オレンジ』、『A』あたりでパソコンのシーケンサーになったんで、じゃあオレも買わなきゃみたいな。めっちゃ影響受けてますよ。僕の機材はほとんど電気と小室の影響です(笑)。JP-8000も、小室がライブでど真ん前で弾いてて、これだ、みたいな。電気がMackie使ってるといえばMackieのミキサーを買い。ファン心理ですね。あの音が出したい、みたいな。
そういえば、テレビ番組でシンセやら何やらが出てくるのが90年代前半の『タモリの音楽は世界だ!』※11で、そこでサンプラーっていうものを知りましたね。中学になっていたから既にシンセは使っていて。でも当時はサンプラーを知らなかったから、なんか声が「ゲゲッゲゲッゲゲッゲゲッ」とかいってるものがあるぞっていう、で、中3の終わりくらいで買いましたね。AKAIのS01。
曲作っている人にとって、サンプラーとの出会いって大きいですよね。今はいきなりサンプラーから入ったりするんでしょうけど、昔はまずMIDIでシーケンス打ち込んで、音作ってみたいな。
m今月の『DTMマガジン』とか「MIDIの基礎を覚えよう」とか、そういう企画じゃん。後乗りでしょ。いきなりサンプリングから入っちゃう。MIDI端子を意識なんかしないでしょ、みんな。MIDIのIN/OUTとかあんまそういうの意識しないでしょ。マブハチって知ってる?みたいな(笑)。オールド世代はここニンマリだから(笑)。
今の制作環境には満足していますか?
mようやく。コア2(Core 2 Duo)になってから。2004年に完全移行しようと思って、Pentium4の3.2を入れたんですが、足りなくて。シンセもソフトウェアで、ほんとにパソコン一個で、っていうのは2004年あたりから。
じゃあそのあたりから、ハードの大きい機材は減らしていこうという方針に。
m減らしたくはない(笑)。減らしたくはないんだけど、作るのには関係ないんだよね、もう。でかいシンセ要らないんだよね、実際は。
それはもうソフトでもハードと同じ音が出るから、という判断ですか?
mいや、作業効率の面かな。曲を作るっていう目的から考えれば、ハードよりもソフトのほうがえらく効率的なので。ただハード楽しいじゃないですか、触ってて。
ハードからPCに移るときに、ハードウェアシーケンサーのほうが作業が早い、ってのはなかったですか?インターフェイスに体が慣れちゃってるというか。
mあったね。暗闇でも、見なくても打てちゃうみたいな(笑)。でも移行にはそんなに手間かからなかったよ。パソコンの設定は大変だったけどね。
じゃあ逆に、今の環境に不満な点はありますか?
m不満な点…、いや、でも相当完成度は高いというか完璧に近いんだけど、レイテンシーと、まだちょっとCPUが100%を超えてしまうケースがあるので、クロックアップは年内にしたいなっていうのはあるんだけど。それが済めばだいぶいいかな。あとやっぱ、キーボードとマウスの操作は面白みには欠けるんだよね。
インターフェイスの可能性はもうちょっと追求していきたいと。
mもっとツマんでいきたいね、いろいろね。
ですよねー。
mだからね、唯一変えてないのがDX7※12。FM7っていうソフトシンセも2004年の移行のときに導入したんだけど、でも僕の場合はハードのほうが音作りが早いんだよね。DX7に関しては。DXだけはなんか譲れなくて。
今は、DX7以外はハードウェアシンセ使ってない、って言っていいと思います。M3は普段弾きと、入力用みたいな用途だから、実際に曲には使ってない。
ソフトウェアシンセの操作には、他にMIDIコントローラなどは使ってますか?
mUC-16もあるけど使ってないね。303でビヨビヨやりたい時だけ繋いで。
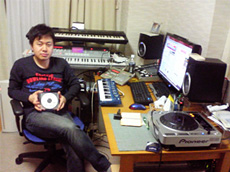
シーケンサーはCubaseで、それ以外はもう全然考えてない。
mえぇー、Live(Ableton Live)気になるけど。みんな使ってるし(笑)。でも、いざ入れると、遊びで終わっちゃうっていうのが分かってる。ようやくですよ、何が自分に合って、何が合わないみたいの分かってきたの。
鏡音リン・レンだっけ、VOCALOID。あれねー、もう最終結論「やっぱ面倒くさいもんはアカン」っていう。買って2時間で終わったね。だから尊敬しちゃうね、今、ミクだの何だのって。
そういえば、TOM-BOYSってロボットっぽいエフェクトの歌モノ多いじゃないですか。そういうときに、VOCALOIDよりも杉山さんの声を加工したほうがイメージに近いわけですか。
m曲を作るときに仮歌が入っていたほうがアレンジしやすいんだけど、やっぱ自分が歌っちゃった方が早いんだよね。かつ、音を外しても今は直せるじゃないですか。
杉山さんのヴォーカルに対しては、もっとこうして欲しい、というような点はないですか?
mないね。基本なくて、でもいつも言ってるのは魂的な部分。音程は直せるけど、雰囲気は直せないんで、魂は込めてくれっていう。そこは技術では直せないので。
じゃあ変な話、VOCALOIDを使わないのは魂が入ってないから…。
mいや、ただ面倒くさいだけ(笑)。面倒くさくなければもっと使ってるかも。
なるほど。TOM-BOYSにおいてヴォーカルは杉山さん、という位置付けじゃないですか。たまにコーラスなんかで深須さんが歌っているのはどういうケースのときですか?
m多分ね、安室ちゃんをプロデュースする小室の感じかもしれない(笑)。

曲と詞の制作はどういう流れで行っているんでしょうか。深須さんが曲を書いて、杉山さんがそれに合う詞を考えて、という流れが多いですか?
mそういうパターンもあるんだけど、けっこうメロディーラインも2人で作るし、『キャンパス・ラヴ』※13も2人で鍵盤弾いて「ここはこうだよね」とかやったよね。
Tでも一緒に、一日でできたっていうのは『キャンパス・ラヴ』ぐらいかもしれない。他の曲だと、深須くんがデモを作って、僕が早めに詞を書いて返して、またさらに深須くんが作ってっていう。
mキャッチボールでね。
何かいいフレーズができたり、いい歌詞が思いついたりして、とっておくことはありますか?
Tノートに書き溜めておいて、それを引っ張ってくるっていうのはあるね。
mこの間myspaceでも発表した『旅立ちのとき』※14っていう曲は、ずいぶん前に作ってあったんだよ。いったんその曲は閉じちゃったんだけど、杉山くんが何かデモ聴かせてよっていうんで聴いたら、「あ、これいいじゃん」ってなって。僕の方には8小節とか16小節とかのループが何十曲も眠っていて、その中から杉山くんがね。僕は全然気に入ってなかったんだけど。
Tたしかサビはもうできてたんだよね。メロディーはあのままで。
m杉山くんに聴いてもらったのは1年前なんだけど、僕が作ったのは2年前とかだよ、多分。でもアレンジが全然違って、bpm170のちょっとハピコア※15寄りの感じで(笑)。
- ※10 「宇宙野菜」TOM-BOYSの2人にDJ Kawasakiを加えた3人組テクノ・バンド。98年結成で、今年で活動10周年を迎える。楽曲の一部はmuzie:宇宙野菜にて聴けるほか、YouTubeでも07年中野heavy sick ZEROでのライブ映像を公開中。
- ※11 『タモリの音楽は世界だ!』テレビ東京系で90年から96年にかけて放送された、音楽をテーマにしたクイズ番組。電気グルーヴがゲストの回では、次々に紹介されるシンセやサンプラーにタモリが夢中になるという印象的な場面も。
- ※12 DX7ヤマハDX7。83年に発売された、FM音源を採用したシンセサイザー。
- ※13 『キャンパス・ラヴ』「TOM-BOYS」の前身であるプロジェクト(メンバーは同じ)、「V'z」による楽曲。母校である中央大学多摩キャンパスを舞台に、往年のトランスやハッピーハードコアへのオマージュを散りばめた、記念碑的トラック。07年発表のコンピレーションCD『VH10』に収録。
- ※14 『旅立ちのとき』08年4月、MySpace上で発表された、「TOM-BOYS」名義の実質的なデビュー曲。ポジティブさと独特のセンチメンタリズムを併せ持った詞が映える、「TOM-BOYS」らしいキャッチーなシンセ・ポップ。当初"Ver.0"として発表され、7月1日、ミックスを新たに正式リリースされたばかり。公式サイトにて公開中。
- ※15 ハピコアハッピーハードコアの略。90年代末から00年代初頭に一世を風靡したジャンルのひとつ。キャッチーな歌ものポップスからのサンプリングと、170bpmを超える早さが特徴の、極端に明るい4つ打ちダンスミュージック。
続いて、音楽の主要メディアがCDからデータに移りつつあることについて伺いたいんですが、お2人はデータで曲を購入することはありますか?
T&mまだ買ったことない。
mあ、ある。YMOの『ライディーン』※16、あれ最初データだけだったので、iTunesStoreで。あれだけだね。
普段どれくらい買ってます?月に何枚とか。
Tいや、僕は全然。買うときは買うんだけど、買わないときは買わない。
mそれは僕も同じだね。CDショップは行きますよ。仕事で疲れた日とか、新宿のタワレコで試聴いっぱいする。レコード屋はとんとご無沙汰で、トランスのあとハピコアをしばらく買ってたけど、今は全然だね。
レコードは実家にあって、ちょっとあれはデジタル化して、DJさんにお渡ししたいなっていうのはあるんだけど。ドラムコード10番※17、オレが持っててもしょうがないでしょ。DJではないので。持っていたい気はあるけどね。

CDってこう、ジャケットがあって、モノとしてあるじゃないですか、そういうものがデータメインの流通に変わっていくことに関しては何かありますか?杉山さんは今iPodなどのシリコンオーディオを使っていませんが、将来的に使ってみたいというようなことはありますか?
Tそうだね。データの方が効率はいいかなと思うけど、ただ今はCDのジャケットデザインも気になったりするし、歌ものだったら歌詞カードを見たかったりするから、そういう点からするとCDかな。
深須さんはどうでしょう。例えば、データなら欲しい曲はすぐ聴ける、しかもちょっと安い、というようなこともありますが。
m欲しい曲だったらCDで買う。なんでなのか、そこをずっと考えてるんだけど、なんかCD。ハード世代なんじゃない?やっぱ。データの物悲しさ(笑)?ちょっと欲しいなとか聴いてみたいなっていうのは、データで買うのはアリなのかなって思うけど。
なるほど。作り手としてはどうですか?その場合もやっぱりCDのほうが、myspaceとか、ネットを使ってデータで公開するよりもいいと思いますか。
mやっぱそうだよね、うん。物理的に残したいというか。達成感があるよね。なんでだろう。
Tアルバムをものとして残したとき、その中で世界観が完結するっていうか。
mああ、それだ。曲の並び順とかね、すごく大事。一枚の作品を作るときは。
Tデータって多分、無限のなかの1データっていう括りだけど、CDだとその一枚の中に世界が詰まっているという。モノとして欲しい、っていうのも、CDだとジャケット、歌詞カード、曲順があるっていう、そこに芸術家がなにかものを作ってそこに魂を残せるという「形としての良さ」を、僕らはまだ大事にしているんだろうね。
m友達から曲をもらうのも、データよりもCDの方がちょっと嬉しいかもしれない。同じ曲なんだけどね。
よくmp3に関して「音質が良くない」なんて言われますが、そういうことは影響していますか?
m音質面はあんまり関係ない。聴く人って音質そんなに気にしてないでしょ。電車の通勤途中で聴く分には十分なんじゃない、みたいな。音質は、聴く側としては気にしないですね。作るときは気にしますけど。
- ※16 『ライディーン』ここでは、07年2月にセルフカバーとして発表された『RYDEEN 79/07』を指す。YMOとしては初のインターネット配信曲。
- ※17 ドラムコード10番スウェーデンのレーベルDrumcodeの10番、Cari Lekebusch"Vänsterprassel Me"のこと。アブストラクトな構成と音使いで、90年代後期のテクノシーンに衝撃を与えた。再発までの一時期は中古価格にもプレミアが付いたほど。
音楽以外で取り組んでいることについて聞かせてください。趣味はありますか?
T僕は、ひとりでいるときはぶらぶら散歩したりとか、喫茶店で本読んだりとか。本は、ミステリーも読んだりするし、あと名言集とか、自己啓発書とか。普段の日常生活のなかで嫌なこととか落ち込むことがあったときは、そういう本を読んだり、もちろん音楽も聴くし。あとは時間があれば一人だったり友達と小旅行とか、普段の環境から外に出たいというのは常にあって、旅とはいかないまでも、ふらっと東京から離れるとかはしたりしてるね。
m僕は趣味が音楽なので大半は音楽は占めますが、あとはお笑いとかゲームやったりとか。
これはちょっと触れておかないといけないんですが、深須さんは大の「タモリ」フリークですよね。タモリはファン暦何年くらいですか?
m物心ついたときから。『魔王』よりも前。
踏み切り→タモリ→『魔王』ですかね(笑)。
mどんなリレーだよっていうね(笑)。ある意味タモリもシステマチックだからね。尺八のSEが始まると、自分でやらずにはいられないみたいな。

深須さんは、音楽は趣味ということですが、仕事にしたいっていうのはありませんでしたか?今もありますか?
mありましたよ。今はなくなりました。一日中音楽をやっていたいというのはあるけど、それも今の社会人生活があるからそう思ってて、実際そうなったときに多分無理だなっていうのはもう分かったんで。そこは普通にサラリーマンをしながら、「あー音楽で飯食いてぇなー」とか思いながら、ジレンマを抱えながら死んでいく、っていう感じでいいかなという風には思っていますけどね。
例えば、TOM-BOYSなり、自分の作ったものが商業ベースの流通に乗せられる機会があればそっちに、というような考えはありますか?
m「wavescan」時代の話が出ますよ、それ(笑)※18。若干商業に乗りかけたじゃないですか、あの時は。あそこで結構色々な体験は、ほんと微々たるものですけど、させて頂いたこともあるので。やっぱ大変だなって思いますね。
じゃあ今は、逆にそこはけっこういいバランスなんでしょうか。通勤のときに頭の中で曲作りのことを考えたりとか。
mいや、仕事中も(笑)。全然オケヒットなってるけど、仕事中も。
だからね、頑張ってほしいね。いま頑張ってる人がいれば、他人に流されちゃダメだね。自分の本当にやりたいことを突き抜けて、商業ベースとか乗ろうと思うと、色んな人が色んなことを言ってくるんだけど、そこはやっぱ自分の我を通すというか、ちょっと考え方変えれば、その商業ベースの悪どい人とかにも乗りながらうまくやる方法はあると思う(笑)。ちょっと違う角度とか、やり方を変えれば、色々まだやれると思うんでね。やり方は色々ありますよ。
- ※18 「wavescan」時代の話wavescan(ウェーブスキャン)はmisutraxとYodyによるトランス・ユニット。2001年にFlamebit Recordingsよりアルバム、『Astroscape』を発表して以降は活動を休止しているものの、楽曲の一部は現在もmuzie:wavescanで聴くことができる。代表曲"Heavenly Body"、"Break Into The Robo"が、TVK系列で放映された連続ドラマ『十三夜』、『HÃTU』のオープニングテーマとしてそれぞれ採用された。
12歳からのハードウェアシンセっ子だったmisutraxさんが、時代の流れを受け、様々な影響を受けながら、2004年にソフトウェア環境への完全移行に踏み込むくだりは、とても興味深いものでした。ブログによれば、最近になってハードウェアを続々と手放しているとのことで、ここでもまた、時代が移り変わろうとしていることを感じました。
また、メディアの点で、CDがCDであることの意義として、「世界が詰まっている」とか、「完成したときの達成感」という話もありました。TOMO-ARCHITECTUREさんは、自身の作品を、音だけではなく、詞や曲順、ジャケットを含めた総合芸術として捉えているようでした。ダウンロード販売のみという形態が珍しいものでは無くなりつつある今、しかし、これもある一面で正しい意見のように思います。
技術革新に端を発する大きな"うねり"を、一方では大胆に、また一方では慎重に受け入れるという柔軟さは、トランスを経由した新しい音によって普遍的な「ポップ」を目指す、TOM-BOYSの音楽そのものなのかもしれません。間もなく発表されるというファースト・アルバムを、楽しみに待ちたいと思います!
聞き手・写真:R3LAYTIONS(R-9,una)/写真提供(一部):misutrax
- 第3回:Yousuke Kaga (Fountain Music) 「聴いたことのない音楽との出会いが、自分の世界を拡げてきた」
- 第2回:Eiji Okada (音楽喫茶 茶箱) 「エンジニアとしての探求心が、"場所"を創り、シーンを繋ぐ」
- 第1回:misutrax & TOMO-ARCHITECTURE (TOM-BOYS) 「2人の音楽少年・出会いからの10年と、その先の"LIFESTYLE"」